![]()
国内外の活動「全部つながっている」 世界の医療団・米良彰子さん
「地球のためにできること」に従事する方々にお話を聞くwith Planetのポッドキャスト。第10回では、世界の医療団の事務局長、米良彰子さんをゲストにお招きしました。
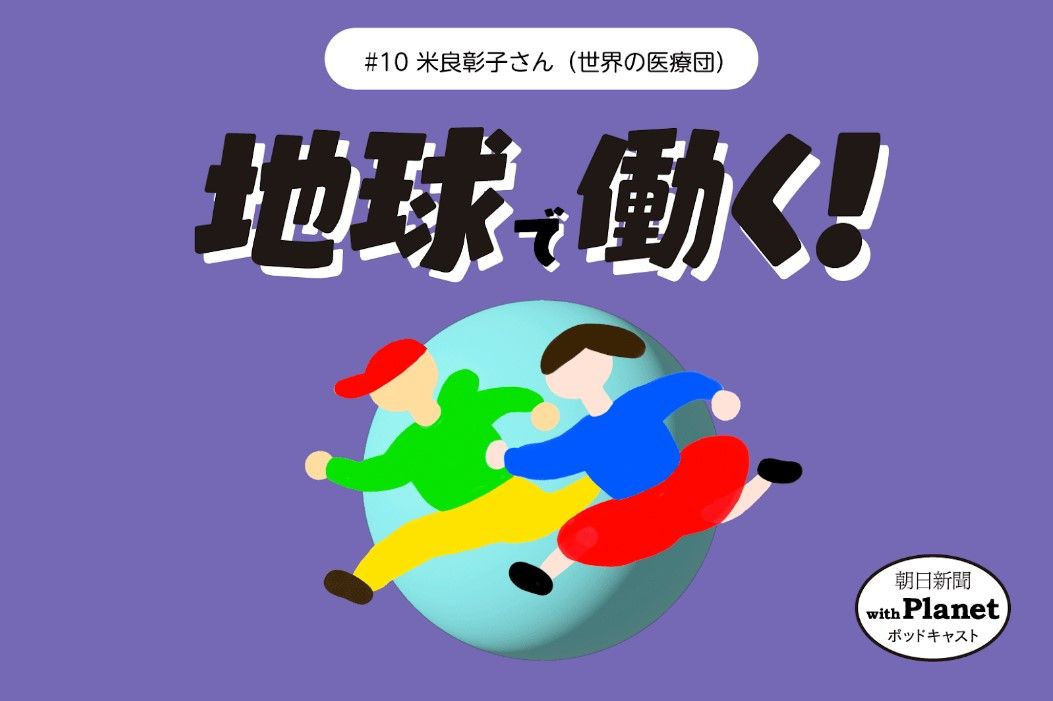
![]()
「地球のためにできること」に従事する方々にお話を聞くwith Planetのポッドキャスト。第10回では、世界の医療団の事務局長、米良彰子さんをゲストにお招きしました。
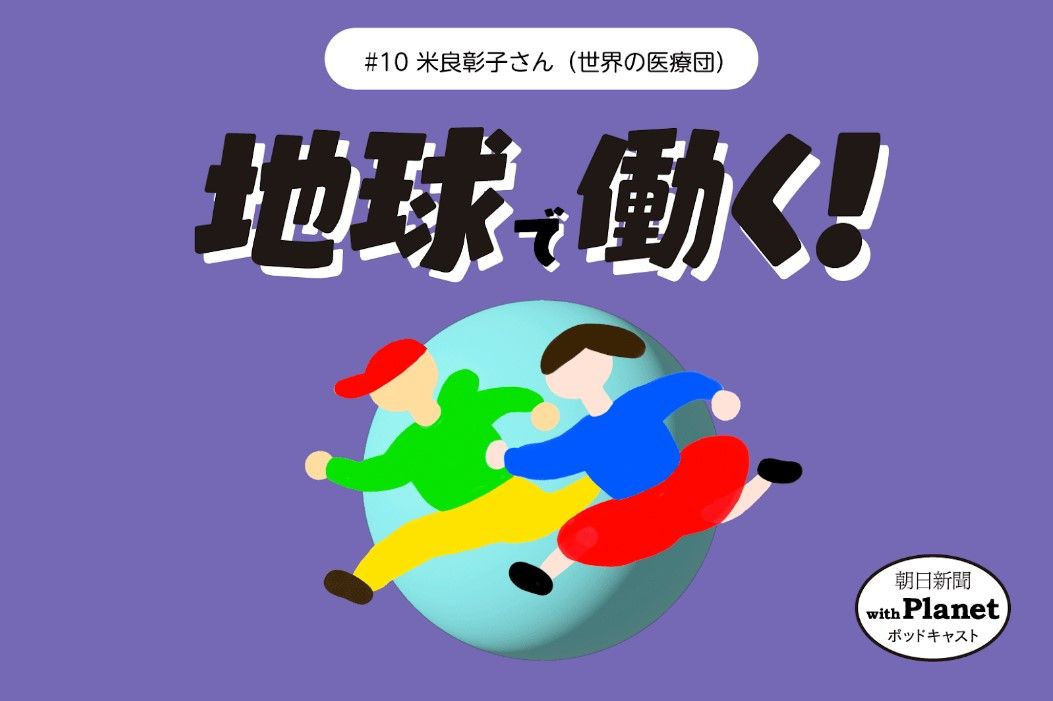
グローバルヘルスやジェンダー問題、人権問題や食料不安。世界にも、日本にも、これらの課題を解決すべく活動している人がいます。NGOをはじめとする「現場で働く人」をゲストに迎えるポッドキャスト「地球で働く!」。第10回では、前回に引き続き、世界の医療団・米良彰子さんをお招きします。ポッドキャスト本編はSpotify、Apple Podcastで配信しています。
with Planetのポッドキャスト「地球で働く!」の第10回では、前回に続き世界の医療団の事務局長、米良彰子さんをゲストにお招きしました。
世界の医療団は、その名の通り、世界の医療を受けられない人々が医療を受けられるよう支援する国際NGO。自然災害や武力紛争などの犠牲者から風土病や伝染病などの疾病に苦しむ人々、難民や少数民族、ストリートチルドレンなどを対象に、さまざまな支援プロジェクトを実施しています。
今回も収録には大学3年生の萩野勇平さんが参加。米良さんには、具体的なNGOの活動や、ご自身のモチベーションについて話を聞きました。この記事では本編の一部を、読みやすいように編集してお届けします。

──具体的に米良さんはどのような活動をされているのですか。
私は医療者ではないので、企画書を書いたり、広報活動をしたり、現場で見たことを行政の方にきっちりお伝えしたりと、幅広くさまざまな活動をしています。コロナ禍のときは保健所と連携し、「ワクチン接種会」という場を作り、ホームレスの方でも希望すればワクチンを打てるようにしました。こうした「場作り」をしています。
──想像するだけでも、行政手続きの壁がたくさんありそうですね。
ワクチン接種のときは行政としてもたくさんの課題を抱えていました。私たちは行政に見落とされがちな人たちを支援していたので、利害関係が一致していたこともあり行政は協力的でしたね。ただ、すべての面において行政がスムーズに動くことはありません。
──世界の医療団は日本ではどのような活動をされていますか。
世界中にいろいろな形で難民の方がいらっしゃいますが、私たちの日本での難民支援で一番多いのはロヒンギャ難民の支援プロジェクトです。難民キャンプの中と難民キャンプを支えている周りのコミュニティーの人たちを対象に、健康教育などをしています。また、ラオスの基礎医療が届いていない山岳地域でも、正しい情報が届くようにする支援もしています。
──「正しい情報」とはどのようなことでしょうか。
例えば、コロナの初期の段階のときに「ワクチンにはお金がかかるのではないか」と思われていて情報がきちんと届いていませんでした。行政の出す文章もわかりづらいという問題もあります。ですからデザイン学校の学生さんに協力いただき、情報をわかりやすく絵で伝えるようにしました。
世界の少数民族で識字率が低い場合でも、正しい情報を伝える必要があります。ロヒンギャのみなさんやラオスの妊婦さんのなかには文字が読めない方もいるので、調査をして現場の方でもわかるように「やってはいけないこと」を絵で伝えるようにしています。その土地の文化に合うものをつくることで、受け入れられやすくなっていると思います。

──広報活動や、企画書などを書いたりと、NGOの活動を継続するためにはさまざまなスキルが必要かと思います。例えば政策提言を行う場合、政治家や役所というなかなか首を縦に振らない人たちの賛同を得るためにはどんなことが必要ですか。
政治家の方はなかなか現場を見ることができません。ですから、日本で動くことが国益だけではなく世界や社会のためにどうつながるのかということを、現場にいる私たちがきちんと「伝え続ける」ことが必要だと考えています。
もしかしたらけんかをしているようにも見えるかもしれませんが、それはけんかでなく、相手を説得し、相手に納得していただくように伝えているのです。そのためには現場のデータも必要で、それをきちんとお見せするということも大事です。
──僕(萩野さん)もデータの大切さは身にしみて感じています。いろいろな活動を聞いていて感じるのは、国外の自分とは関係がないような地域の支援、たとえば誰も知らないようなラオスの山岳地域の支援を、日本の私たちがしなくてはいけないのか?という問いが出てきます。米良さんの「私がやらなければいけない」というモチベーションはどこから来るのでしょうか。
モチベーションは「全部つながっている」というところですね。ウクライナの戦争で日本のパンが値上がりしているように、「関係ないよ」とは言えません。全部がつながっていて、現場が少しでも変わって、「やっぱりやってよかった」と感じられることが大きいですね。でも、私1人ではできないから今度は「誰を巻き込むか」を考えて活動しています。
日本は地震などの災害を経験してきて、東京都では「防災ブック(防災ハンドブック)」が各家庭に配られています。このことを同じ地震大国であるイタリアの同僚に話すと、とても興味を持って、彼らが国の防災提言をするときに使われています。そうやってどこかで全部がつながっているのです。
──その活動はどこか世界の一部だけのものではなく、積もり積もって世界全体を良くすることにつながっている。そして活動によって「良くなっている」ことを実感できるということなんですね。
(続きはPodcast本編で。Spotify / Apple Podcast)
米良彰子さん
兵庫県宝塚市生まれ。スポーツメーカーで海外営業として働く傍ら、阪神淡路大震災時より多言語放送局の立ち上げ・運営に携わる。アメリカの大学で国際関係学を学び修士号取得。国際機関でのインターンなどの経験を経て、NGOで必須サービスや、食料・栄養分野でのアドボカシー・キャンペーンに関わる。バングラデシュ・ベナン・ブルキナファソ・ウガンダ・ネパール・インド・バヌアツなど南アジア、アフリカを拠点に現場で国際協力に携わった後、2020年3月から現職。(世界の医療団HPから)