![]()
「怒り」「悔しさ」がモチベーション 難民支援協会の石川えりさん
「地球のためにできること」に従事する方々にお話を聞くwith Planetのポッドキャスト。第14回では、前回に引き続き、難民支援協会の代表理事、石川えりさんをゲストにお招きしました。
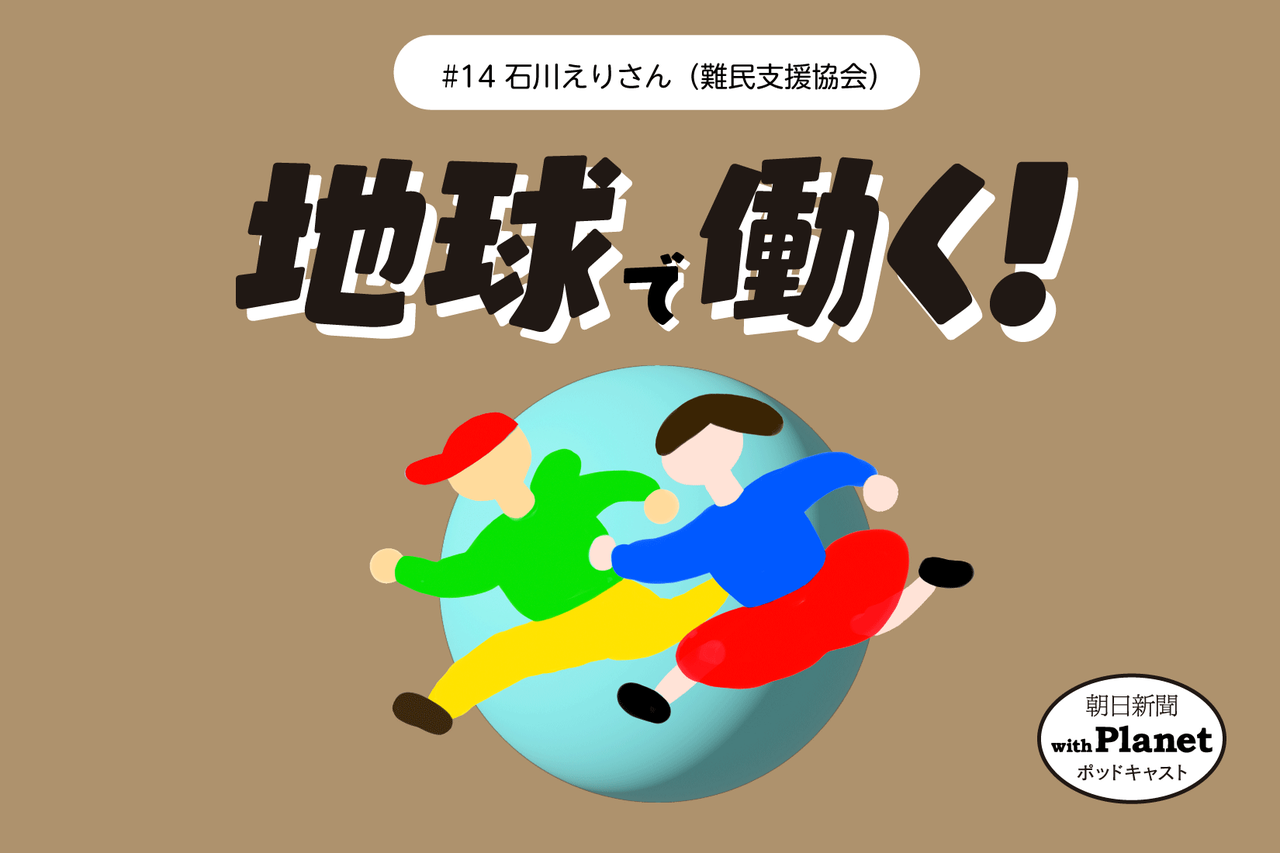
![]()
「地球のためにできること」に従事する方々にお話を聞くwith Planetのポッドキャスト。第14回では、前回に引き続き、難民支援協会の代表理事、石川えりさんをゲストにお招きしました。
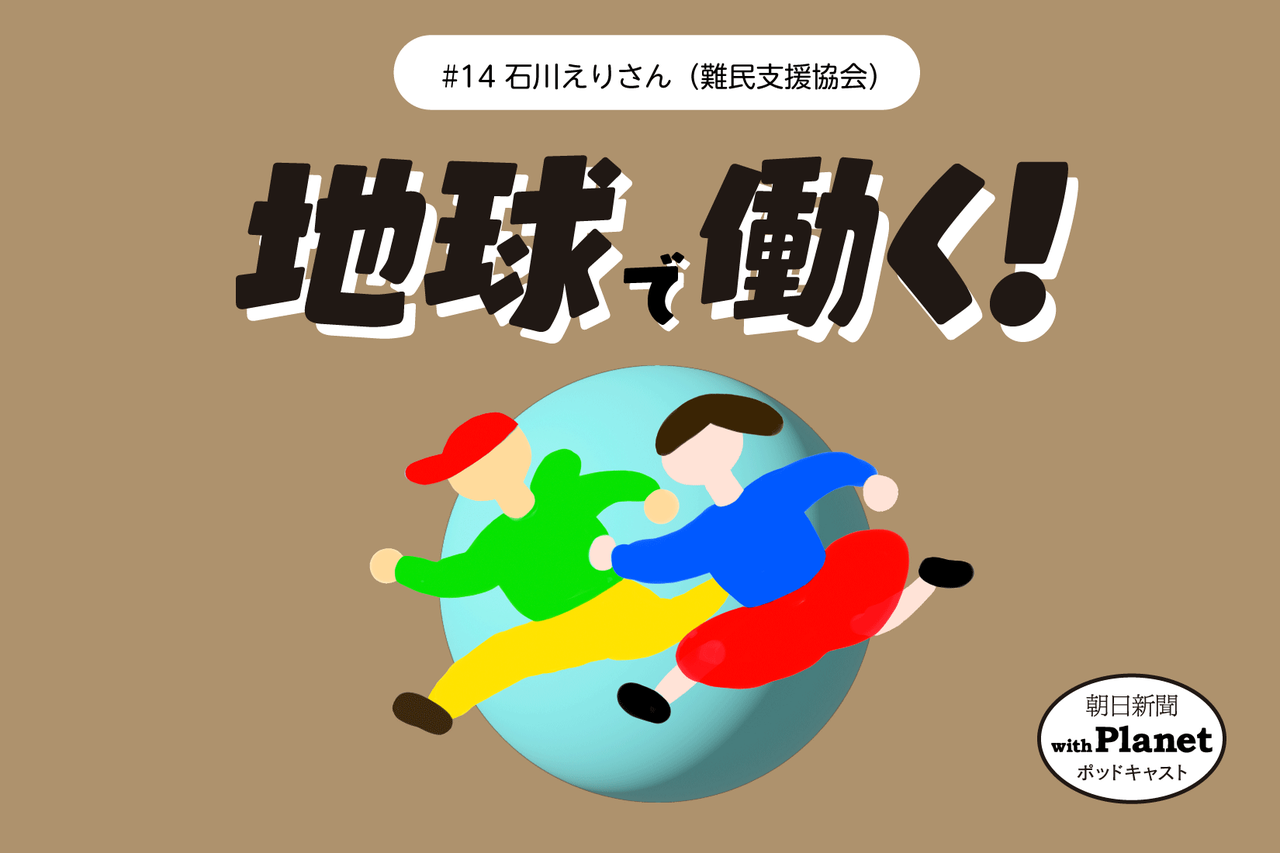
グローバルヘルスやジェンダー問題、人権問題や食料不安。世界にも、日本にも、これらの課題を解決すべく活動している人がいます。NGOをはじめとする「地球のためにできること」に従事する方々にお話を聞くwith Planetのポッドキャスト。第14回では、前回に引き続き、難民支援協会の代表理事、石川えりさんがゲストです。ポッドキャスト本編はSpotify、Apple Podcastで配信しています。
with Planetのポッドキャスト「地球で働く!」の第14回では、前回に引き続き、難民支援協会・代表理事の石川えりさんをゲストにお招きしました。
高校時代から難民問題に関心を持ち、大学卒業後に難民支援協会の立ち上げに参加した石川さん。収録には人権問題に関心がある大学3年生の石岡紗織さんが参加し、難民支援を続けるモチベーションについてお話を聞きました。
この記事では本編の一部を、読みやすいように編集してお届けします。

──難民支援協会は、具体的にどんな活動をされているのですか。
難民支援協会は1999年に設立された、日本に逃れてきた難民を支援している認定NPO法人です。難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会を目指すことをビジョンとしています。
例えばシリアからの難民に対しては、日本への入国後すぐに他団体と連携して生活支援を行い、シェルターを提供しました。日本に来た難民のなかには、一定程度の時間を経て就労できるようになる方もいます。そういった方には日本語教育を提供し、就労に向けた自立のための支援も行います。日本社会の中でコミュニティーを形成して暮らす方には、地域の自治体との橋渡しのような総合的な支援を提供しています。
2022年度は72カ国803人の方への支援を行いました。日本に入国して間もない、スーツケースをガラガラと引きながら「1週間前に成田空港に着きました」という方と向き合うことも多くあります。手持ちのお金が尽きてしまって「昨日から何も食べていない」という方も事務所にいらっしゃいます。そういった方々と日々向き合い、お話を聞き、カウンセリングをしていく。食料を手配したり、事務所で食事を提供したりもしています。
──支援を必要としている難民の人々の数は増え続けているのではないでしょうか。人材面、資金面でも限りがあるなかで、ベストの支援を行うために心がけていることはありますか。
限られたなかで支援していくには、優先順位をつけざるを得ないこともあります。結果、支援を提供できない人も出てきますが、それは「団体の限界」として認めざるをえません。であればこそ、まずは現場での説明を尽くすこと、そして支援に向き合い続けることが大切です。
スタッフも、支援できるときよりも支援できないときのほうがずっと疲弊します。ホームレス状態にあるとわかっている人に「今日は支援ができません」とお断りするとき、一番つらいのはもちろんそこで帰らざるをえないご本人ですが、私は断る当人であるスタッフのつらさに寄り添うことも心がけています。

──石川さんは30年間も難民支援に力を注いでいます。どんなモチベーションで続けられているのか、教えてください。
少し言うのがはばかられますが、根底にあるのはやりがいというよりも、怒って、悔しくて続けているということが大きいです。こんな(ネガティブな)感情でいいのだろうかと感じていたこともありましたが、国連難民高等弁務官だった緒方貞子さんがかつて「怒って続けている」とおっしゃっていたのを聞いて、「これでいいんだ」と少しほっとしました。
現場にいると、どうしたって「不正義」を目にすることもあります。日本に来た難民の方が、警察を見たら思わず逃げなきゃいけないと感じてしまうこと、シェルターがないこと、最低限の生活が送れないこと、どうしたらいいかわからない人たちが無期限で収容されること……。
いろいろな不正義を見る中で、「これでいいわけがない」「どうしてこんな社会なんだろう」、「これほどまでに人を苦しめる制度とはなんだろう」と思います。どうしても変えたい、諦めたくない、という思いが強いですね。
──そうした不正義に立ち向かうために、日本に住むわたしたちには、何ができるでしょうか。
日本は戦争が「日常」ではありません。戦争や人権侵害、迫害から逃れる難民も、身近な存在だとはいえません。だからこそ、考え続けてほしいです。一人ひとりがご自身のなかにある関心のスイッチを押す。そうすることで、少しだけでも景色は違って見えてくるはずです。
新聞やSNSで、「難民」という言葉を少しでも意識し、関心をもっていただけるとうれしいです。日本社会をどういうふうにしていくのか、私たちの社会をどう考えて作っていくのか、一緒に考えられればと思っています。(続きはPodcast本編で。Spotify / Apple Podcast)
石川えりさん
1976年生まれ。上智大学卒。1994年のルワンダにおける内戦を機に難民問題への関心を深め、大学在学中から難民支援協会(JAR)立ち上げに参加。大学卒業後、企業勤務を経て2001年にJARへ入職。直後からアフガニスタン難民への支援を担当、日本初の難民認定関連法改正に携わり、クルド難民国連大学前座り込み・同難民退去強制の際にも関係者間の調整を行った。2008年1月から事務局長となり2度の産休をはさみながら活動。2014年12月に代表理事就任。第5回日中韓次世代リーダーズフォーラム、第2回日韓未来対話にそれぞれ市民セクターから参加。共著として、「支援者のための難民保護講座」(現代人文社)、「外国人法とローヤリング」(学陽書房)、「難民・強制移動研究のフロンティア」(現代人文社)ほか。2児の母。上智大学非常勤講師。一橋大学国際・公共政策大学院非常勤講師。