![]()
1人で始めた「小さな支援」 マレーシアの課題解決に挑む後藤愛さん
マレーシアに移住し、1人で社会貢献活動を始めた後藤愛さん。規模は小さくても、支援の届きにくい人たちに目を向けニーズを探ります。瀬名波雅子さんが聞きました。
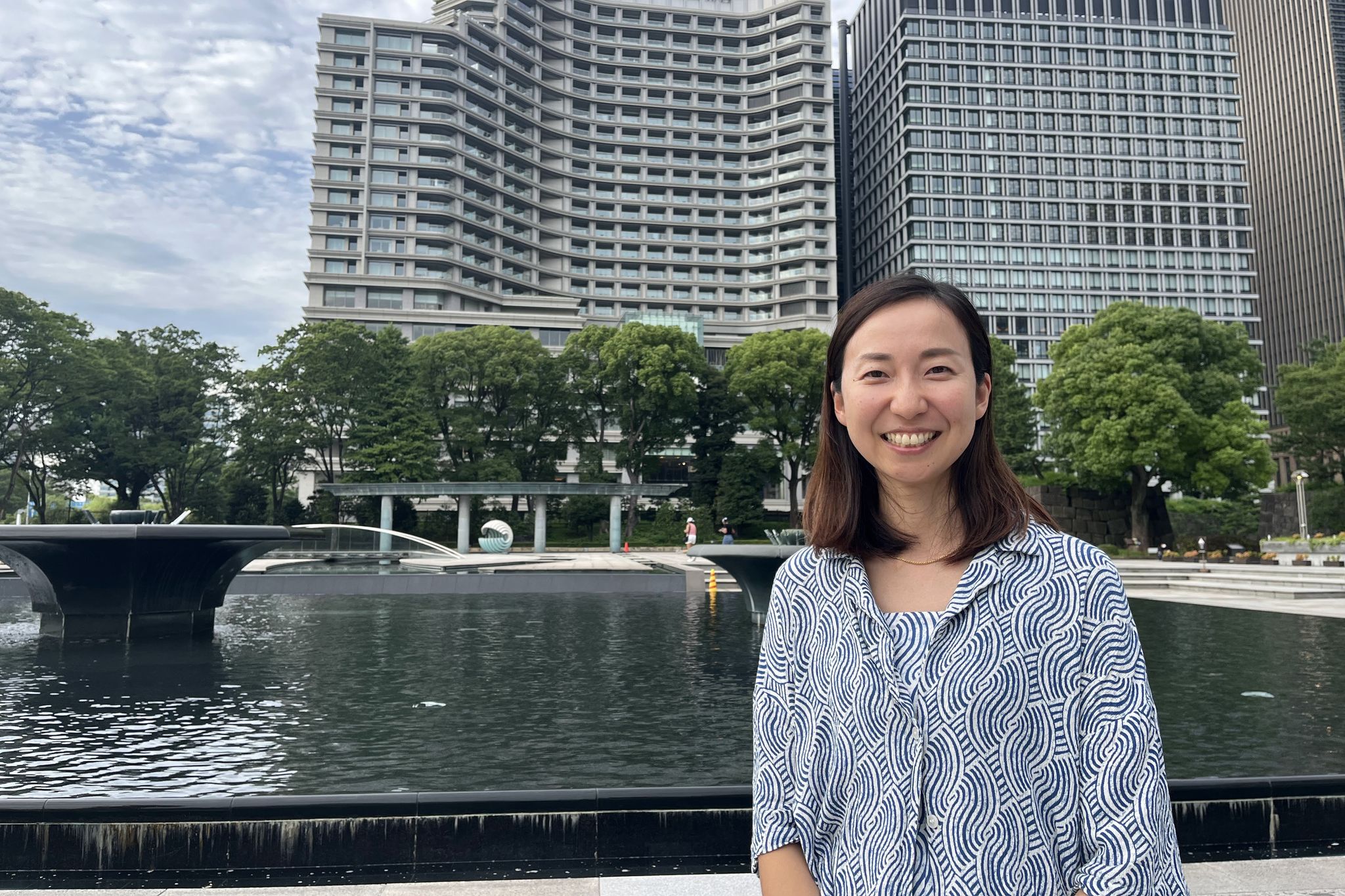
![]()
マレーシアに移住し、1人で社会貢献活動を始めた後藤愛さん。規模は小さくても、支援の届きにくい人たちに目を向けニーズを探ります。瀬名波雅子さんが聞きました。
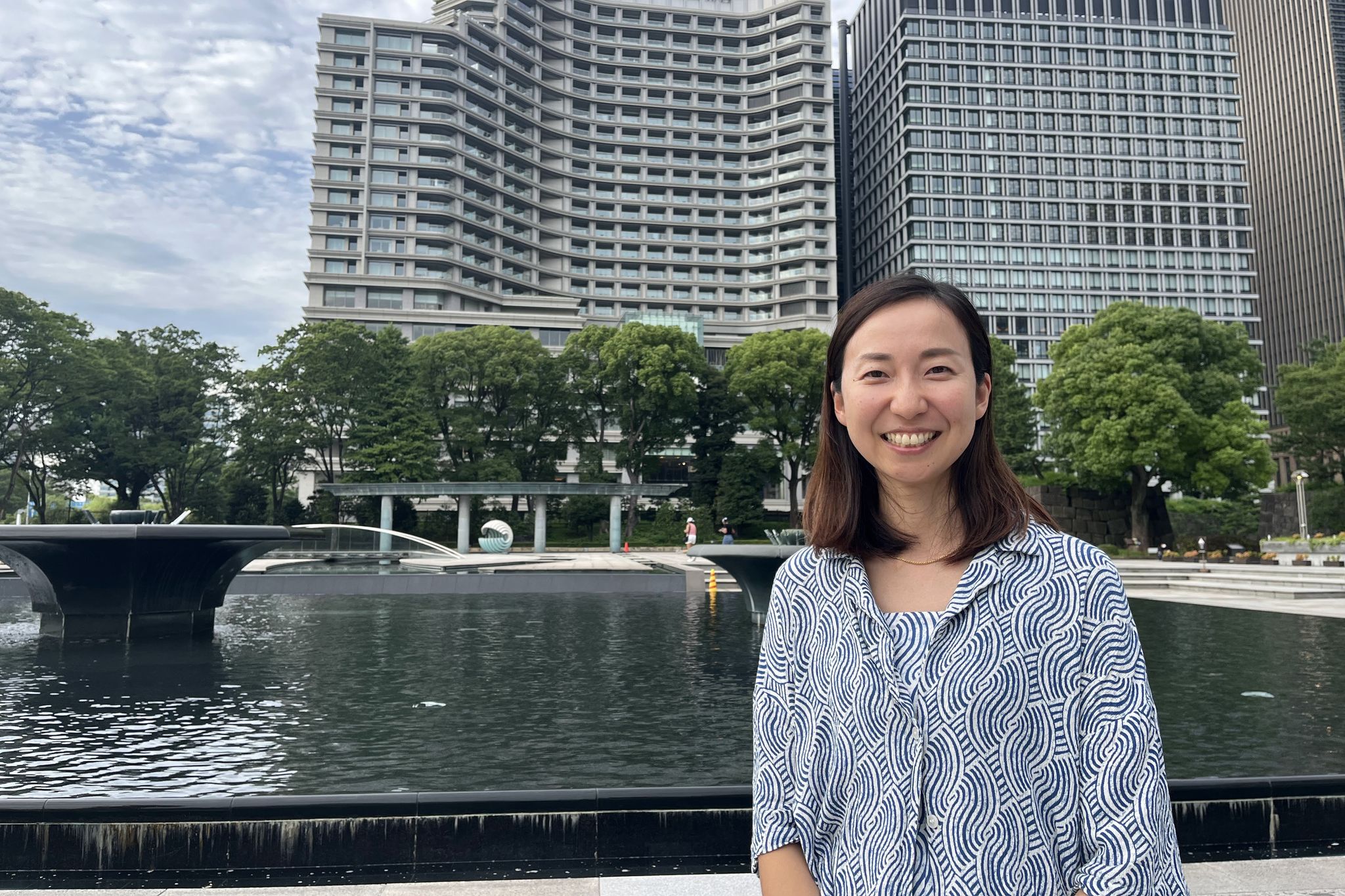
安定した職を辞め、個人発のフィランソロピー(社会貢献)事業を始めた一人の女性がいます。東南アジアのマレーシア・クアラルンプールに住む後藤愛さん。彼女はこの地で「マイクログラント」と呼ばれる小口支援金をNGOや社会的企業に提供する活動を始めました。マレー半島とボルネオ島北部から成るマレーシアは、多民族・多言語・多宗教国家として知られています。1970年代以降、民族間格差の是正を実現するための政策が進められた一方で、今も都市部と開発が進まない地域の格差が著しく、見過ごされたままの課題もあるといいます。後藤さんに、マレーシアでの事業について聞きました。
――後藤さんは現在、マレーシアでNGOや社会的企業に小口支援金を提供し、社会やコミュニティーに対し、影響力のある取り組みを応援する活動をされています。まず、その事業内容について教えてください。
私は2021年から、マレーシアで「CHANGEマイクログラント(以下、CHANGE)」という活動を行っています。マイクログラントとは、直訳すると「小口支援金」という意味です。一口10万円程度の小口支援金をNPO、NGOや社会的企業のプロジェクトに提供し、小さくとも持続的なインパクトを出す活動を応援しています。
これまでの3年間で、女性、子ども、若者が知識やスキルを習得する研修や、小規模ビジネスの改善などのプロジェクトを支援先に選び、計18件の支援を実施してきました。マイクログラントの原資は私と夫個人の日本での不動産収入で始め、今は寄付も受け付けています。昨年は3人から10万円ずつ寄付があり、30万円のファンドレイズができました。今年は昨年の3倍以上の額を集める見通しで動いています。
――どのような経緯で、マレーシアでマイクログラントの事業を始めることになったのでしょうか。
さまざまな背景が重なってたどりついた事業です。幼い頃から国際協力や国際交流に携わる仕事に就きたいと思っていましたが、今振り返ると自分の思いをより深く考えるようになったきっかけは、2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロです。当時私は日本の大学からの交換留学で、アメリカにいました。ニューヨークから電車で2時間くらい南に行った、フィラデルフィアです。そのとき、テロが起きました。留学先の大学ではニューヨークで働く卒業生も多く、たくさんの先輩たちが亡くなりました。
この出来事を機に、グローバル社会における強者と弱者について考えるようになりました。世界や社会の中で、排除されて居場所がない、虐げられていると感じる人たちがいる。そうした人たちの鬱屈(うっくつ)した思いが積み重なって、同時多発テロにつながってしまったと思いました。私はますます、自分がどういうふうに世界と関わっていきたいかを真剣に考え始めました。
世界は複雑で長い歴史があり、一人の力で変えられることなどたかが知れているかもしれません。それでも、世界中で起きている分断を減らすためにも、私は困難を抱えていたり抑圧されていたりする人たちの側に立ち、彼ら、彼女らを応援する力になりたいと望んでいることに気づきました。
大学卒業後は世界で国際交流文化事業を行う政府系組織・国際交流基金に就職し、アメリカの大学院留学やインドネシアでの駐在を経て、2020年に家族でマレーシアに移住しました。移住先をマレーシアに決めたのは、ビザの取りやすさや、英語が準公用語で通じること、治安が割と良いこと、日本との距離、時差を考えてのことです。マレーシアに移住後、ずっと温めていた自分の事業を実行に移そうと、18年間勤めた国際交流基金の仕事を辞め、マイクログラントの事業を始めました。
――組織を離れ、一人で始めた理由は。
自分が関心をよせる社会課題に対し、小さく目立たなくても、社会にとって大切な活動をしている人たちを応援したいと思ったからです。
政府や国連が予算や時間を投入して解決に乗り出そうとしている課題も多くあり、そうした動きは必要だと思う一方、本当に困っている人の課題は、政府からの支援が届かなかったり、社会に課題だと認識されないまま深刻化したりしてしまうことがあります。そうした課題をなんとかしようと動いているNGOや社会的企業の活動を後押ししたいと思いました。自分もそんなチームの一員になり、解決に動く人たちを増やしていきたいと思ったのです。
――マレーシアで、政府からの支援が届かないまま、問題が深刻化している課題にはどのようなものがありますか。
様々なものがありますが、この活動を始めてみて大きな課題だと認識したのは、「ステイトレス(無国籍)」の問題です。CHANGEでは子ども・若者・女性の支援活動をメインにマイクログラントを提供していますが、困難な状況にいる人たちの背景にステイトレスにまつわる問題が横たわっています。
マレーシアには、近くのフィリピンやインドネシアなどから紛争を逃れるためや出稼ぎのために来る人たちがいます。その一部はマレーシア国籍も市民権もないまま住み続けており、そうした人たちはかなりの数いるといわれています。政府にとっては、不法滞在者およびその子どもたち、ということになります。
マレーシアは子どもの権利条約に批准していないこともあり、国民以外が無条件に義務教育を受けられるようにはなっていません。市民権を持たない親から生まれマレーシアで育った子どもたちは、マレーシアにいながら公教育を受けることができず、将来仕事にも就きにくい。親も正式な滞在許可がないため公的支援にアクセスできず、生活が苦しくても声を上げられない、という負の循環があります。
ステイトレスの人たちに関しては統計もないため、何人ぐらいいて、どのくらいの収入があるか、どのような生活を送っているかなど、全く把握されていません。
私自身はもともとこのステイトレス問題を解決しようと思って活動を始めたわけではありません。ただ、支援を必要としている子ども・若者・女性と出会おうとすると、少なくない頻度でこの課題が浮上してきて、大きな問題なのだということに気づきました。法的な枠組みの制約と、現実とのはざまで、政府にとっても市民社会にとっても解決が非常に難しい社会課題です。
――そうした課題に対してどのような支援をしているのでしょうか?
国籍や市民権がない場合、大きな企業への就職や公務員になることはできないので、自分で屋台やレストランなどのスモールビジネスをして生計を立てていくことになります。教育と就労が大きな課題で、CHANGEではその解決に取り組むNGOと連携しています。

東マレーシアのサバ州という地域で、ステイトレスの子どもが通える寺子屋のような学校を作り、教育を提供しているNGOがあります。サバ州は、クアラルンプールから飛行機で3時間ほどの場所に位置し、あまりまだ開発が進んでいない地域です。そこで活動を行うNGOがCHANGEのマイクログラントに応募してきたので支援を決め、子どもの送迎に学校に来る母親たちの就労支援プログラムにミシンを寄贈しました。作った洋服や雑貨を近所の市場で売り、作り手が現金収入を得るという流れです。
1期目が非常にうまくいったので、昨年から2期目を開始し、今度は同じNGOが運営する別の学校でプログラムを実施しています。参加者はお母さんと学校の生徒たちがほとんどですが、時折お父さんも交ざって、しかもそのお父さんはミシンがとても上手で、皆で和気あいあいとやっています。
このプログラムを通じて現金を手にしたことで、ガスコンロを買って毎日の家事が楽になったり、自信をつけて次のビジネスを考えたりするようになったなど、参加した人たちにさまざまな変化が生まれています。

――CHANGEでは他にどのような事業を支援されていますか?
ステイトレスとはまた別に、マレーシア人女性たちの地域活性化活動も応援しています。同じサバ州に、ハーブと食用花を栽培している会社があります。この会社は業績がよく、さらなる販路拡大と商品の品質管理を、近隣農家の女性たちと共にできないかということで、CHANGEがその研修費をサポートしました。女性の所得向上と生活改善を目指したプロジェクトです。
今年3月にはこの会社を訪れて、研修に参加した女性たちに話を聞きました。「研修を受けていなかったら何をしていましたか?」という質問に「ただ家にいただけですね」という答えもありました。「ハーブの育て方を教えてもらったので、今は育てて納品する仕事をしています」と自信をもって答える姿に、女性たちの前向きな変化を感じました。

―― CHANGEでは、応募があったプロジェクトから、どのようなプロセスを経て支援する団体を決めるのでしょうか。審査の公平性や透明性という観点で気を付けていることはありますか。
CHANGEはもともと私個人で始めた活動でしたが、その後マレーシア人のアドバイザーを2人迎え、今年3月にはマレーシアで非営利活動を行う法人格を取得しました。
私たちがマイクログラントを出すのは、女性・子ども・若者の生活を改善するもので、ソーシャルインパクト(社会課題に対する影響)をもたらすものと決めています。具体的には創造的な教育機会の提供、キャパシティービルディング(能力の向上や構築)、コラボレイティブラーニング(協働学習)の事業に力を入れている団体です。受益者となる女性・子ども・若者への直接的な支援というよりも、研修やトレーニングを行うことで中長期的に変化が生まれる仕組みづくりの初期費用として、マイクログラントを使ってもらいたいと考えています。
審査は私とアドバイザー2人で行っています。審査基準として、独創性や実現可能性など複数の項目を設定し、申請書類を見ながら私たち3人がそれぞれ応募プロジェクトに点数をつけます。全体の点数を足して順位を付けた後、審査会議を行って全員で中身を見直します。申請書類の他に、口コミを調べたり、直接知っている団体についてはその内容をシェアしたりもします。

助成金の審査というのは私も前職で行っていたのでノウハウがありますが、難しいこともあります。どの団体もプロジェクトのありのままを申請用紙に書けるわけではないからです。たとえば申請書類があまり的を射ていなかったり数字も間違えたりしているけれど、団体の評判はとてもいいし、おもしろそうなことが書いてある。逆に、申請書はきれいに仕上がっているけれど、よく読むと趣旨がCHANGEとずれているようにも見える。
こうしたケースでは、どう判断するべきか悩みます。そこで大事にしているのが、審査をする全員が納得するまで議論するというプロセスです。多数決ではなく、それぞれが情報を持ち寄って話し合い、全員で合意したうえで支援候補を絞っていきます。
この助成事業のプロセスの中で、「応募自体が団体の成長に役立つことがある」ということにアドバイザーからの指摘で気づきました。応募団体は、募集要項を読んで申請書類を記入することで、自分たちの仕事を見る角度が変わったり、「こういう見せ方ができるのでは」「こんなこともできそう」と考えたりしますから、視点が変わるきっかけにもなります。候補先の上位に残っている団体にはオンライン面接を行うことがありますが、選考時のやり取りを通して団体の成長やスキルアップを感じることもあります。

――今後はどのような事業展開を描いていますか。
私たち夫婦の日本での不動産収入を原資に始めたこの事業ですが、昨年は3人から10万円ずつ寄付がありました。これ以上の寄付を受けるなら法人化したほうがよいだろうということで、今年法人化しました。これからは監査も入れて、経理報告も出し、透明性を高めたうえでさらに寄付を集めて少しずつ活動を続けて広げていきたいです。
個人発の、まだまだ駆け出しの事業ではあるものの、こうした一人ひとりの小さな行動が積み重なっていくことが大事だと思っています。実現したいことがあるなら、地味でも地道に一歩ずつ前へ進んでいく。そうした個人の行動の積み重ねで少しずつ世界は良い方向に向かっていくのだと信じて、私自身も挑戦を続けていきたいです。
ごとう・あい 1980年生まれ。一橋大学法学部(国際関係論専攻)を卒業後、2003年独立行政法人国際交流基金に就職。2008年、フルブライト奨学生としてハーバード大学教育大学院教育学修士号(Ed.M.国際教育政策専攻)取得。2012年から2017年、同基金ジャカルタ事務所(インドネシア)に駐在し、東南アジア域内と日本との文化交流事業に従事。2021年に同基金を退職し、現在マレーシアでCHANGEマイクログラントに携わる。マレーシアなど海外移住する現役世代日本人の生き方、働き方、育て方を綴るエッセイ『越境する日本人』(白水社Webふらんす)を連載中。家族は夫と子ども3人。