![]()
「マラリアゼロ」に期待される日本の役割とは 熱帯医学専門家に聞く
マラリアの撲滅のためには、予防、早期診断、治療など多面的、かつグローバルな取り組みが必要です。国立国際医療研究センターの狩野繁之さんに現状と課題を聞きました。
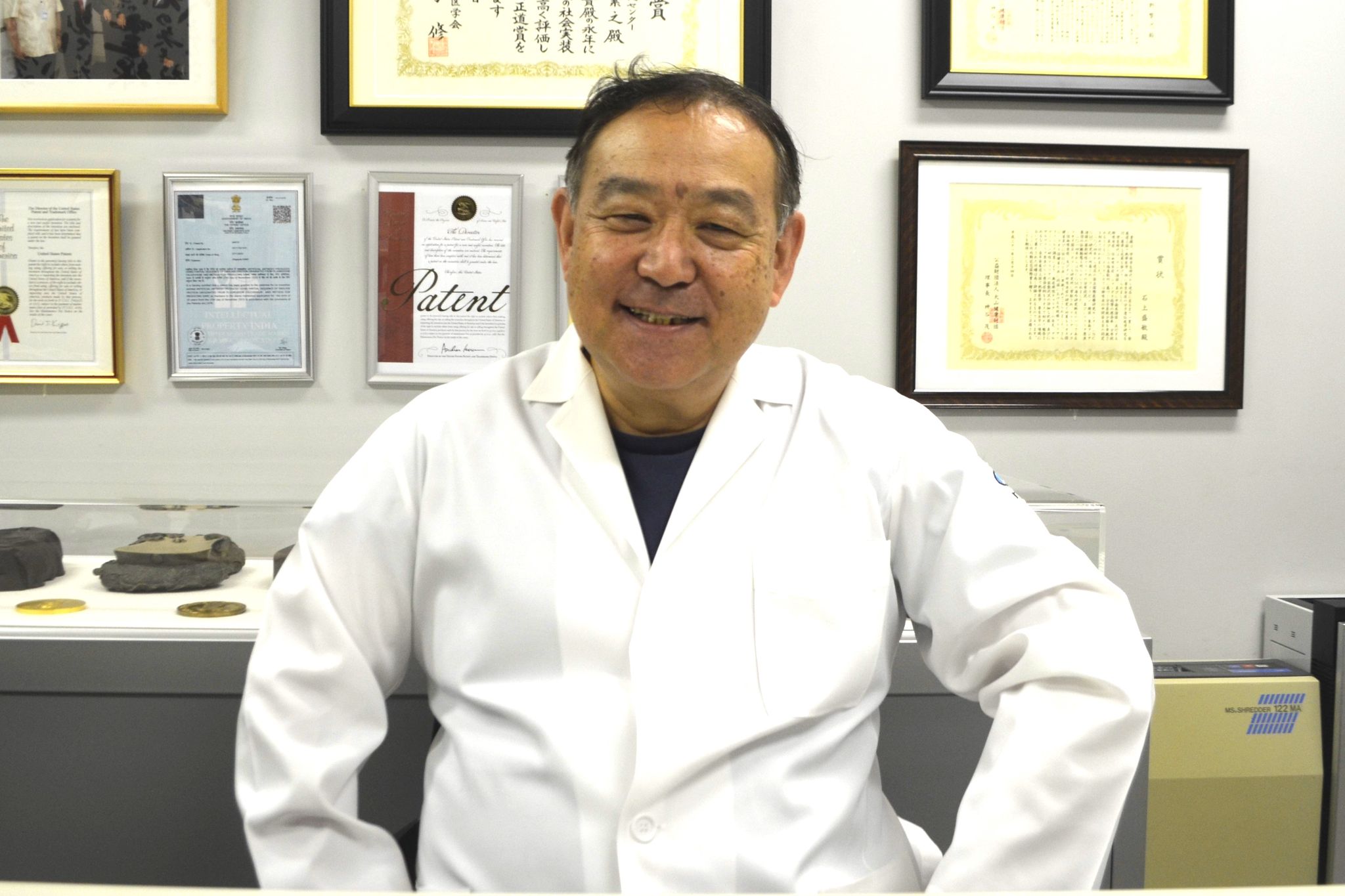
![]()
マラリアの撲滅のためには、予防、早期診断、治療など多面的、かつグローバルな取り組みが必要です。国立国際医療研究センターの狩野繁之さんに現状と課題を聞きました。
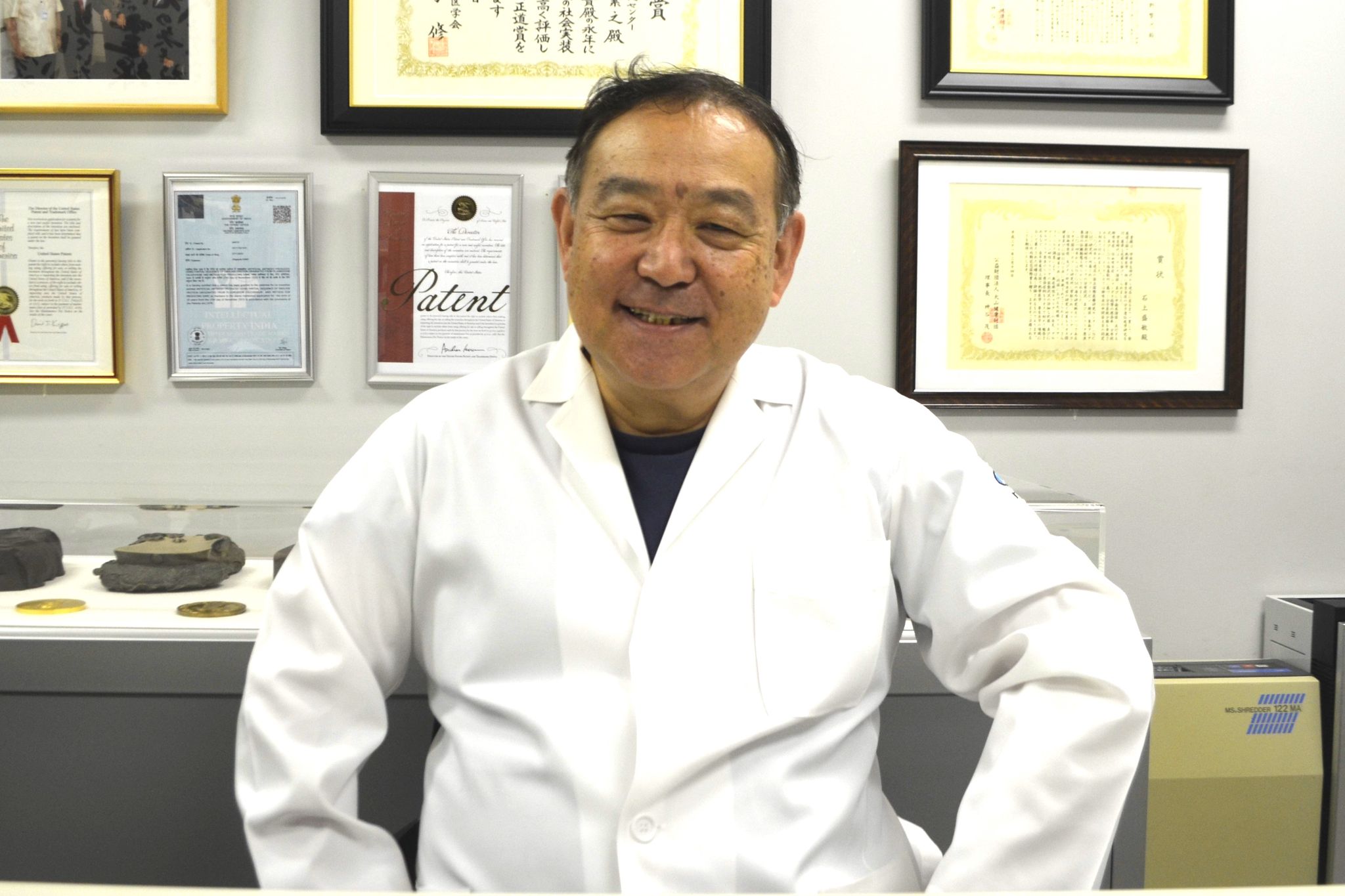
長く熱帯感染症の研究を続けている国立国際医療研究センター研究所、熱帯医学・マラリア研究部の狩野繁之部長は「人類はサルからヒトへと進化した頃からマラリアと闘ってきた」と言う。闘いの歴史、現状や課題をどう見ているのか。そして、日本にできることとは何かを聞いた。
――最初にヒトとマラリアの歴史について教えてください。
歴史上の人物で言えば、古代エジプトの王ツタンカーメンがマラリアにかかったことが確認されています。ツタンカーメンは戦車から落ちて、ひどい複雑骨折をしたと言われているのですが、加えて、遺伝性の血液疾患もあって、貧血だったらしいです。骨折により大量出血して死に至ったという見方もありますし、あるいは貧血にマラリアが重なった可能性もあります。日本でも平清盛がかかった瘧(おこり)はマラリアだったという説があります。
ただ、平清盛の頃は高熱が出ても加持祈禱(きとう)くらいしかできなかった。病原体の正体であるマラリア原虫の存在と、蚊に刺されることで感染するという経路が分かったのは、19世紀も終わり近くになってからでした。ここに至ってようやく、「そうか、蚊に刺されなければよいのか」と認識されたわけです。ちなみに、原虫と感染経路を見つけた2人の学者は後に、ノーベル生理学・医学賞をそれぞれ受賞しました。
――原虫や感染経路が分かって100年以上がたちました。現状はどうでしょう。
2000年までには撲滅できるだろうと言われていましたが、大変残念なことにまだそこに至っていません。
世界保健機関(WHO)のリポートの推計(中央値)では、2021年の感染者は2億4700万人、死亡者は61万9千人です。2023年3月までの新型コロナウイルスの累計の感染者は6億7700万人、死者は688万2千人でした。コロナの年間の感染者数とほぼ同じくらいですので、かなり多い。まだまだ身近な疾患です。
この間、WHOなどは、2015年の感染者数2億3千万人と死者数57万7千人をベースに、2020年までの5年間で40%、2025年までに75%、そして2030年までに90%減らそうという目標を立てて取り組んできました。しかし、残念ながら2020年段階では減らすどころか、感染者数は6.5%増え、死者数も8.3%増えてしまいました。
――どうして悪化したのでしょうか。
WHOは新型コロナの影響が強かったという見方をしていて、もっと結果が悪くなってもおかしくなかったが、各国が頑張ってくれたおかげで、そこまで悪くならなかった、と説明しています。確かに新型コロナによって、マラリア対策地域で検査をしたり薬を届けたりする人が自由に動けなくなったケースがありました。それだけでなく、最初の頃は、対策地域の人たちと一緒に働く欧米の人たちが対象国に行けない、あるいは物流自体が止まってしまうという問題もありました。一方で、対象地域でもヘルスシステムがきちんと確立されていた場所では、欧米の人たちがいなくても、地元スタッフやボランティアが一生懸命活動を続けて、マラリア感染がそれほど増えなかったところもありました。普段から人材育成をし、ヘルスシステムを強化するという明確な目標を持って支援をすることの必要性を感じました。
――感染者が多い地域や特徴はどうでしょうか。
先ほど「新型コロナとマラリアの年間の感染者数はほぼ同じ」と紹介しましたが、分布はまったく違います。新型コロナの感染者が多いのは欧米など先進国ですが、マラリアはアフリカを中心とした途上国になります。世界84カ国で流行していて、インド、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイ、ミャンマー、パプアニューギニアなどのアジア太平洋地域の国々も含まれます。
感染者と死者の9割以上が、いわゆるサブサハラ、アフリカの国々に集中しています。死者の年齢層も新型コロナと違っています。新型コロナは高齢者が多いのですが、マラリアは死者の8割が5歳未満の子どもたちです。マラリアは予防できないわけではない。それでも、何十万人という子どもたちが、「蚊に刺される」というそれだけの理由で亡くなっているのです。

マラリアにかかっても、薬を一生のむ必要はありません。数日で良いのです。そもそも蚊帳に入って寝れば蚊に刺される機会をかなり減らせます。だけどやっぱり貧しさがあり、また、世界的な関心が低いために、対策を必要としてる人たちに支援が届いていないのが現状です。
――これからの対策はどう進めていくべきでしょうか。
最初にすべきは、やはり予防です。蚊と人の接触を断つことです。マラリアは主に4種類が知られていて、このうち最も危険なのは、重症化しやすく、死に至ることもある「熱帯熱マラリア」です。熱帯熱マラリアの原虫を運ぶ能力の高いガンビアハマダラカは、ヒトへの指向性が高く、動物とヒトが一緒にいる場所でもヒトを刺しにいきます。ただ、夜間に家の中で刺す傾向があることが分かっているので、蚊帳に入っていれば安全です。糸の中に殺虫剤を染み込ませている蚊帳は長く使えて、予防効果が高いことも分かっています。

しかし、蚊帳は適切に使わなければいけません。せっかく蚊帳をつっても、暑いからと外に寝ては意味がありませんし、穴が空いていたら効力は下がります。本来の用途とは違い、魚取りに使ってしまうような例もこれまでにはありました。「命を守るための価値あるものだ」と、理解してもらわなければいけません。
ただ、蚊には多くの種類があり、吸血行動も生息地も卵を産む場所もかなり違います。地域によっては、蚊帳だけでは不十分で、卵を産むところに薬剤をまいたり、水辺に砂がたまって流れがよどまないようにしたり、といった対策も必要になります。アジアでは近年、5種類目のサルマラリアが広がっています。流行の中心はマレーシアですが、ラオスやタイなどでも報告例が出てきました。さらに、殺虫剤への抵抗性を持った蚊への対応、温暖化によって生息地が広がることにどう対処するか、も考えていかなければなりません。
――対策をしていても刺される場合もあります。
接触を完全に断つことはできません。次に来るのは、早期診断と治療です。理想的には、発症してから24時間以内に治療が始められるようなシステムを構築しなければいけません。24時間以内というのは、実は日本のような国にとっても別の理由で難しいのです。
ペイシェンツ・ディレイやドクターズ・ディレイとも言うのですが、流行地から帰国して高熱が出ても、患者がマラリアを疑わない、その後も医者がマラリアを疑わないことがあるからです。日本の場合、発症から48時間くらいで治療が開始される例が多く、アフリカより時間がかかっていて、手遅れになってしまうケースもあるのです。
――早期診断がとても重要ということですね。
かつては顕微鏡検査が基本でしたが、今は迅速にマラリア原虫に由来する抗原タンパクを検出するキットがたくさん開発されています。誰でも、どこでも、いつでも検査ができるので、WHOもキットを使った診断を認めています。ただ、偽陰性が一定程度あります。日本では、マラリア原虫のDNAを増幅して検出する複数の方法が開発されています。一定の技術レベルと環境整備が必要ですが、検出感度は非常に高い。今後、日本の技術が貢献できる分野ではないでしょうか。
――ワクチン開発はどうなっていますか。
マラリア原虫は非常に複雑なライフサイクルを持っているので、ヒトの体内のどこにある時を狙ってワクチンを開発するか、が悩ましい問題でした。試行錯誤を経て、英製薬大手のグラクソ・スミスクラインが、原虫が肝臓に入って増殖することを防ぐワクチンを作り、感染を4割ほど減らせるという結果を示しました。これを受け、WHOが2022年9月、アフリカの中程度から高度流行地域の子どもたちに、このワクチンを推奨しました。
現在、アフリカで83万人の子どもにワクチンを打つプログラムがまさに進められているところですが、課題の一つが、3回(現段階では4回)打たないといけないということなのです。流行地というのは、基本的に蚊帳や薬がなかなか届けられない場所です。そこに先回りして複数回のワクチンを打つというのは、コストパフォーマンスとしてどうなのか、という議論が当然起こりました。WHOも、ワクチンを従来の対策と組み合わせて、どう活用するかを考えています。

――「ワクチンができたから、もう安心」とはいかないのですね。
そうです。ただ、最近、オックスフォード大学の研究チームが開発したワクチンで、7割以上の予防効果があったという発表があり、WHOも推奨しました。開発はこれからも進んでいくでしょうが、問題はどこから資金を得るかです。マラリアのワクチンを必要としているのは、アフリカなどの貧しい国々です。裕福な国も必要とした新型コロナのワクチンは開発リスクが分散され、承認された後にはワクチン代金が戻ってくる仕組みでしたが、マラリアは違います。最も経済的に脆弱(ぜいじゃく)な地域の、最も貧しい患者に届ける必要があるのです。国際機関はもちろんですが、市民社会や外部のパートナーを巻き込んだ、全く新しいワクチン開発のモデルが必要になると考えています。
――「マラリアゼロ」に向けて、日本にできることは何でしょうか。
日本もずっとマラリアに苦しんできましたが、本州では1959年に、当時はまだアメリカの統治下にあった沖縄でも1961年に排除できました。そこには様々な対策があったのですが、なかでも学校保健をベースとして、マラリアなどの感染症に対する正しい知識を家庭や地域に広げていったことが大きかったのです。
こうしたヘルスシステム構築の分野で、日本はリーダーシップを発揮してきましたし、今後も大きな役割を果たせると思います。また、殺虫剤抵抗性を持つ蚊に対して、より効果的な薬剤を染み込ませた蚊帳をどう開発するかといった技術への期待も大きいでしょう。
〈かのう・しげゆき〉
国立国際医療研究センター研究所熱帯医学・マラリア研究部長。1959年生まれ。群馬大学大学院医学研究科博士課程修了(寄生虫学)。ラオスやタイなどアジアのマラリア研究や対策にも長く携わっている。2022年度には国際関係の分野で活躍した人に贈られる「外務大臣表彰」を受けた。